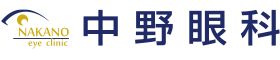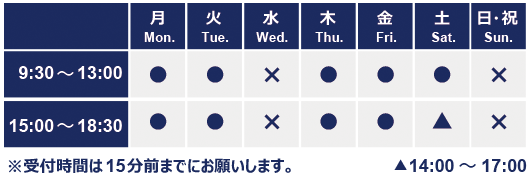1. はじめに
ブルーライトカット眼鏡は、パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスから発せられるブルーライト(青色光)を軽減する目的で広く普及しています。しかし、近年の研究ではその効果に対する疑問が提起されており、特に小児への使用に関しては慎重な姿勢が求められています。本コラムでは、ブルーライトカット眼鏡の効果に関する最新の研究結果と、日本眼科学会の提言について詳しく解説します。
2. ブルーライトとは
ブルーライトは、可視光線の中でも波長が短く、エネルギーが強い光で、主にデジタルスクリーン、LED照明、太陽光から発せられます。一部では、ブルーライトが目の疲労や睡眠障害の原因とされ、視力への悪影響が懸念されています。ブルーライトの波長はおおよそ 400〜500ナノメートル(nm) に位置しています。
3. ブルーライトカット眼鏡の効果について
3.1. 眼精疲労への効果
近年の複数の研究によると、ブルーライトカット眼鏡が眼精疲労の軽減に及ぼす効果は限定的であると報告されています。
研究結果の例:2021年のランダム化比較試験では、ブルーライトカット眼鏡を使用しても、通常のクリアレンズと比較して有意な差は見られませんでした。
解釈:眼精疲労の主な原因はブルーライトではなく、長時間の近距離作業や不十分な瞬き、画面の明るさなど、他の要因が影響していると考えられています。
3.2. 睡眠への影響
ブルーライトがメラトニンの分泌を抑制し、睡眠障害を引き起こす可能性があることは知られています。しかし、ブルーライトカット眼鏡による睡眠改善効果についても、科学的根拠は限定的です。
4. 小児への使用に関する日本眼科学会の提言
日本眼科学会は、2021年に「小児へのブルーライトカット眼鏡の処方は推奨しない」という提言を発表しました。この提言の背景には以下の理由があります。
- 成長過程への影響:小児は光に対する感受性が高く、自然な光の刺激が成長や発達に重要であるとされています。特に、パープルライト(紫色光)は小児の目の健康維持において重要な役割を果たしており、これを過剰にカットすることで近視の進行を促進する可能性が指摘されています。パープルライトの波長はおおよそ 360〜400ナノメートル(nm) であり、ブルーライトの波長と非常に近接しています。そのため、ブルーライトをカットすることでパープルライトの吸収も妨げられる可能性があると考えられます。
- 科学的根拠の不足:小児に対するブルーライトカット眼鏡の有効性や安全性についての十分なデータが存在しないため、不要な眼鏡の使用は避けるべきとされています。
5. デジタルデバイス使用時の推奨対策
ブルーライトカット眼鏡に頼るのではなく、以下のような対策が眼の健康維持には効果的です。
- 20-20-20ルール:20分ごとに20フィート(約6メートル)先を20秒間見つめて目を休める。
- 画面の明るさ調整:周囲の環境に合わせて適切な明るさに設定する。
- 適切な作業距離の確保:画面と目の距離を適切に保つ。
- 定期的な瞬きの意識:意識して瞬きを増やし、ドライアイの予防を心がける。
6. まとめ
ブルーライトカット眼鏡は広く利用されていますが、その効果には科学的な裏付けが十分とは言えません。特に小児への使用については、日本眼科学会が推奨していないことから、慎重な対応が求められます。デジタルデバイスの使用による眼の疲労は、適切な生活習慣と目の使い方を工夫することで十分に予防できます。
参考文献
- Sheppard AL, Wolffsohn JS. “Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration.” BMJ Open Ophthalmology. 2018.
- 日本眼科学会. “小児へのブルーライトカット眼鏡の処方についての提言.” 2021.
- Singh S, et al. “Effectiveness of blue-light filtering spectacle lenses in reducing eye strain from digital devices: A randomized controlled trial.” American Journal of Ophthalmology. 2021.