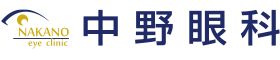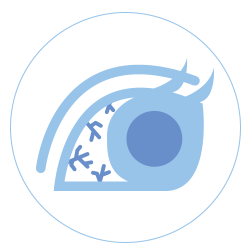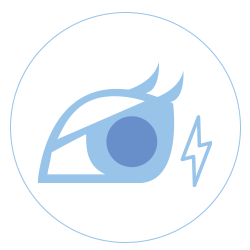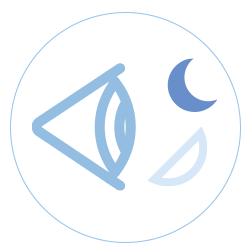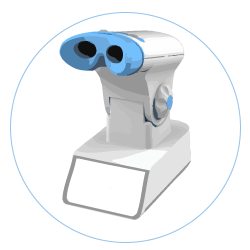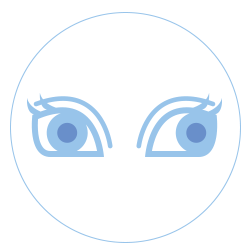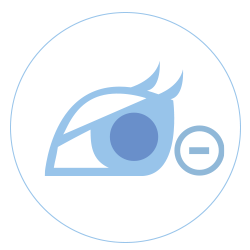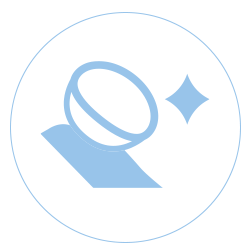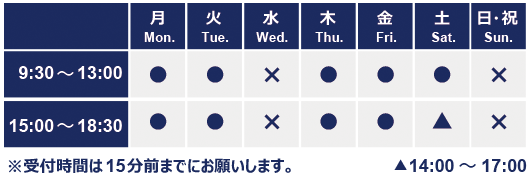診療内容(疾患別)

白内障は、眼の水晶体が濁り、透明性が失われる病気です。

緑内障は、眼の中の圧力が上昇し、視神経が損傷を受けることで引き起こされる眼の疾患です。

結膜炎(けつまくえん)は、結膜と呼ばれる眼の表面を覆う薄い膜の炎症を指します。
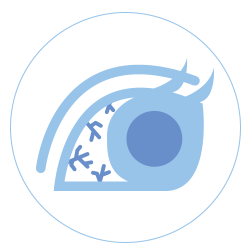
ドライアイは、目の表面が十分に潤っていない状態を指します。

ものもらいは、マイボーム腺と呼ばれるまぶたの脂腺に膿がたまることで起こる病気です。
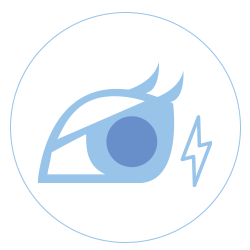
閃輝暗点(せんきあんてん、英: scintillating scotoma)は、視野内のある部分が見えにくくなる現象を指します。

ぶどう膜炎(ぶどうまくえん)は、眼の中で重要な部分を占めるぶどう膜が炎症を起こす病気です。

眼精疲労は、長時間のデバイス使用や集中作業などによって引き起こされる、眼の疲れや不快感のことを指します。

眼瞼けいれん(がんけんけいれん)は、まぶたが無意識に痙攣する状態を指します。

飛蚊症は、眼球内のゼリー状の物質である硝子体中の微小な粒子や線状の影が、視野に浮かんでいるように感じられる症状です。

糖尿病網膜症は、糖尿病患者が高血糖の影響を受け、網膜に損傷が生じる症状です。

網膜動静脈閉塞疾患は、眼の網膜の血管に問題が生じ、血液の流れが制限される症状です。

加齢黄斑変性は、年齢の進行とともに網膜の中心にある黄斑部が変性する病気で、視力の低下を引き起こすことがあります。

中心性漿液性脈絡網膜症(ちゅうしんせいしょうえきせいみゃくらくもくまくしょう)は、網膜の一部である黄斑部に液体がたまる病気で、視力の低下を引き起こすことがあります。

網膜ジストロフィは、遺伝的な異常によって引き起こされる一群の網膜疾患で、これにはさまざまな種類があります。
近視進行抑制治療
日照不足や近見作業(近くを見て作業すること)の増加により、子ども達の近視の増加・重症化が問題となっています。その一方で様々な研究により、近視の進行を予防する方法が開発されています。
なお、近視進行抑制治療は保険の適応は出来ません。全て自費診療となります。
近視進行抑制治療の詳細はこちら>>
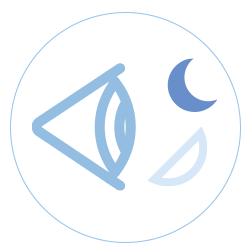
オルソケラトロジーは、内側に特殊なデザインが施された、高酸素透過性のハードコンタクトレンズ(オルソ-K レンズ)を寝ている間に装用する近視矯正法です。
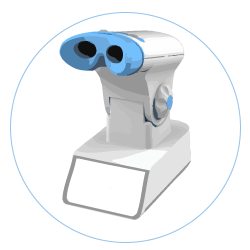
レッドライト治療法は、波長650nmの赤色光が近視の進行抑制に強い効果があるというというものです。
小児眼科
小児眼科は、子どもの目の健康を維持し、視覚の発達をサポートするために専門化された医学の分野です。小児眼科では、さまざまな視覚障害や目の異常に対する診断、治療、管理が行われます。以下に、小児眼科で行われている主な領域と活動をいくつか挙げてみましょう。
小児眼科の詳細はこちら>>
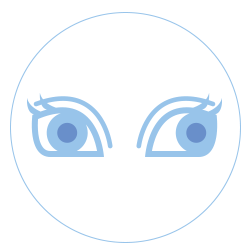
斜視とは左右の目の視線が、違う方向を向く状態を意味します。
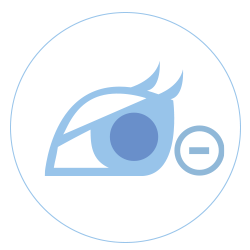
弱視(あるいは「視力低下」)は、通常の視力発達が妨げられ、視力が適切に発達しない状態を指します。
コンタクトレンズ
コンタクトレンズの詳細はこちら>>